↑ ↑
日々のブログ更新の励みになります。是非クリックをお願い致します。
こんにちは、ロスジェネ世代のベンベンです。
今回は「老後2,000万円問題」に関して、私が周りの方々に話を聞いた中で、世の中の人々が考えている誤解について考察をしたいと思います。
「老後資金2,000万円問題」の3つの誤解について考察

「老後資金2,000万円問題」、この言葉のきっかけは2019年6月に発表された金融審議会市場ワーキング・グループの報告書です。この報告書では、平均的な収入の年金受給者が毎月5万円の赤字になり、これを平均年齢まで生きた場合に必要なお金が約2,000万円になるというものでした。
報告書のおかげで、老後の資産作りの重要性が高まったのは間違いありませんが、同時に日本人のお金に関する知識のなさに驚いた方も多いのではないでしょうか。
以下に老後2,000万円に関する3つの誤解についてご紹介します。
誤解①:そもそも、みんな一律に2,000万円不足するわけではない

報告書が連日報道された2019年には、多くのメディアが「2,000万円」という数字を使い、その数字が資産形成セミナーのタイトルになるなど、「退職後の生活には2,000万円が必要だ」と一方的な報道がされていました。
私の周りにもよく分かっていないのに「2,000万円も貯まる訳ないよね!」とか言っている人も多くいて、このような一方的な報道を鵜呑みにするのではなく、自分の家庭はどうなのかという視点で考える事が必要だなと改めて感じました。
具体的な数字を用いていかないと不安な方は、山崎元氏が著作で提唱している下記の「人生設計の基本公式」を参考に試算してみて下さい。

この基本公式のなかで、重要なのが老後生活費率(x)になります。我が家では70%にてしましたが、平均も70~80%ですので、一度試算して頂ければ自身の老後に必要な貯蓄率についてイメージが湧くと思います。
山崎元氏の著作も合わせてご紹介します。非常に分かりやすく率直に書かれているので、読んでいて面白いですよ!
誤解②:「老後資金2000万円」=「2000万円の赤字」という意味ではない

「公的年金の支給月額の平均値」と「退職後の生活の支出額の平均」の差額である「5万円強」は、実のところ「赤字」ではありません。
退職後の生活費=退職後年収=年金収入+勤労収入+資産収入
退職後の生活費は3つの収入で賄われます。
- 「年金収入」:公的年金など
- 「勤労収入」:働いて得る
- 「資産収入」:現役時代に積み上げてきた「退職後の生活のための資産」からの引き出し
この3つを合わせて退職後年収と呼びますが、前述の「赤字」という言葉は、実は赤字ではなく「資産収入」でカバーされる金額ということがわかります。
「赤字補填」ではなく、“使うべきお金”というかたちで変換した方がよいですね。
誤解③:退職時点までに2,000万円を用意する必要はない

これは多くの方が思っていることですね。多くの人がそれを退職までに資産収入で2000万円を用意しておかなければならないということです。
資産収入については資産運用のみで得るという考えの方が多いですが、これまで投資した元本も含まれます。
資産収入を生み出す「資産」 = 元本 + 収益(現役時代の運用収益+退職後の運用収益)
上記の式でいくと、現金や預金を取り崩して生活費に充てることも「資産収入」ですし、株式の配当や値上がり益、投資信託の分配金や値上がり益も「資産収入」の対象になります。
この式で重要なこととして、収益には退職後の運用収益も見込んでいますので、資産収入すべてを現役時代に用意しなくてもいいということです。
元本と現役時代の運用収益の合計が退職までに用意する対象で、退職後の運用収益は60歳以降の運用がもたらすものです。
まとめ

今回は「老後資金2,000万円問題」の3つの誤解について考察しました。
現在、老後資金を全く準備できていない方でも、
- これまでの労働で年金収入がある
- 体も心も十分であり、70歳くらいまでは働く意欲がある
- 50代くらいから始めた資産運用での配当金・運用益が見込める
上記のような方は2,000万円という数字に踊らされずに、自分のペースで着実に老後資金を貯め豊か老後を実現出来ると思います。
我が家では現在1,200万の資産になりましたが、住宅ローンもまだ32年ある状況ですので、目標としては
- 55歳までに住宅ローン完済
- 60歳時点で株式など運用資産5,000万
- 50歳以降は地元九州で負担のない仕事で家族仲良く過ごし、年に1回は海外旅行に行く
上記のような人生を歩めるように「今を大切にしっかりと頑張っていきたい」と思っています!

以下の本は私が最近読んだ本で最も勉強になり、自身のこれからの人生に活かしていきたいと思った素晴らしい本です!
老後が不安な人は下記の2つの本を読むことをおススメします!
今回も最後までお読み頂き、ありがとうございます。
以上、ベンベンでした!
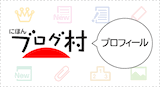



コメント
[…] […]